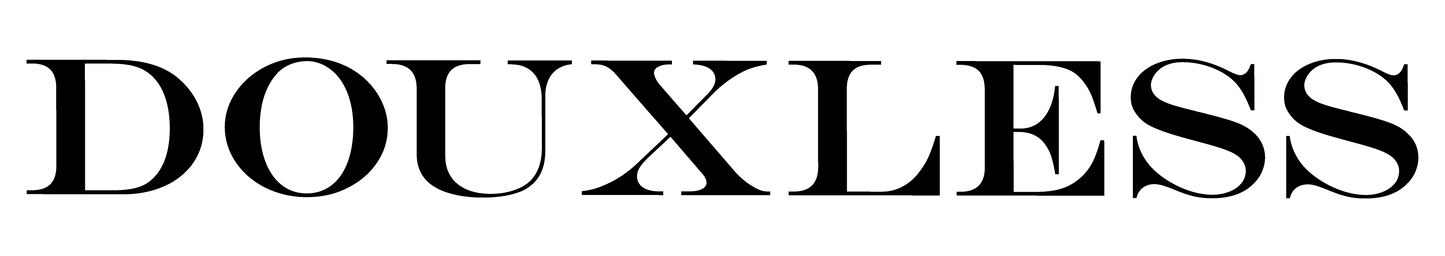開発者たちの思想 一問一答
taner 塚越慎之介 × YOILABO 播磨直希
扉を開けると、磨かれたグラスと静かなBGM。中野の「taner」は、DOUXLESS開発者の一人「塚越慎之介」氏が切り盛りするレストランだ。
レストランのテーブルで“飲む人も飲まない人も”同じ熱量で楽しめる一杯を——その理想は、日々のサービスの積み重ねから立ち上がった。

写真左:塚越 慎之介(DOUXLESS開発者)、写真右:播磨(DOUXLESS ブランドオーナー)
1. DOUXLESSは「ジュースでも、お茶でもない」

Q. 塚越ソムリエがDOUXLESSの開発に携わることになったきっかけは?
播磨: お酒を飲めない方々にインタビューを重ねる中で、「料理と楽しめる非アルコール飲料」への確かな需要を感じました。
ならば日本でトップクラスの人に頼もうと考え、株主経由で、当時すでにノンアルコールペアリングを切り拓いていたsio(代々木上原)をご紹介いただき、そこでソムリエを務めていた塚越さんに依頼することになったんです。
Q. 開発初期に感じていたノンアル市場の課題は?
塚越: レストランの現場で選択肢が乏しかったこと。ぶどうジュースや上質なジンジャーエールはあるけれど、リストに載る“主役”がいない。
当時も面白い商品は多少あったのですが、文化として根づくには、ソムリエ側の提案余地と、ゲスト側の体験価値を両立できる飲み物が必要でした。

Q. 「Not juice, Not tea」というコンセプトの狙いは?
播磨:よく「ジュースですか? お茶ですか?」と聞かれますが、どちらでもありません。まずそこを明確に否定しておきたい意図があります。
少し抽象的な話ですが、人は先に与えられたラベルに味の認識を引き寄せられがちです。たとえば「これはジュースです」と伝えると、評価はジュースの枠に収まってしまう。お茶でも同じです。
だからこそ既存の枠組みにラベリングされないよう、最初に“どちらでもない”と伝える必要があると考えています。
Q. ワインの代替ではなく“新しい選択肢”として目指した立ち位置は?
播磨: ワインにもジュースにも、それぞれの良さがあります。無理に既存の枠組みに寄せるのではなく、「液体」という制約だけをかけて、お客様が本当にほしい体験を形にしていく。
イミテーションではなく、新しいカテゴリーとして存在させたいと考えました。
Q. 他ブランドにはないDOUXLESSの視点は?
塚越: レストランシーンを中心とした、食中のシーンを前提にしていること。単体でおいしいのはもちろん、料理と合わせることで一段レベルが上がる設計です。
例えば単体で美味しいジュースは濃厚なものが多いんですが、濃いだけでは香りは出にくい上、料理と合わせづらい。
果汁の“厚み”を特性として活かしながらも、その余白にハーブやスパイスを差し込んでいく。濃度勝負ではなく、香りと味のバランスをとって完成度を高めるという発想です。
2. 味づくりの要点は「多層の立体感」

Q. 原料(果汁・茶葉・ハーブ・スパイス)の役割分担は?
塚越: 果汁はコクと果実感、茶葉は渋みとボディ、ハーブ&スパイスは香りと刺激。ワイン的なイメージで立体をつくる感覚に近いです。
組み合わせで層をつくり、飲み進めると表情が変わるように設計しています。
Q. 一般的なノンアルコールとの製法上の違いは?
播磨: キッチンベースの発想です。アフターブレンドで、素材ごとに最適抽出したパーツを最後に合わせる。オールインワン抽出では原料の良さを最大化できない。
わかりやすく例えるなら、各食材を別途で調理していき、最後に出汁で全体をまとめるように一体感をつくる筑前煮に似ています。プロの現場と同じ考え方・精度をそのまま持ち込んでおり、サプライチェーン全体まで含めると一般的な飲料の4〜5倍の手間がかかっています。
Q. 料理との相性を生む要素は?
塚越: 一般論としては、五味の相性や香りの同調、コントラスト、ボディやテクスチャーの整合。ぼくはこれのうちどれかがあっていれば、という考えではなく、複数が重なる必要があると考えています。
例えば香りだけが同調しながら、質感や味の重なりがズレてしまうと、全体のバランスがチグハグになる。それは安価なフレーバーティーを飲んだ時の感覚に近く、体験に違和感が生じてしまうんです。
DOUXLESSはそのあたりも考慮して、ドンピシャのペアリング、というよりはなるべく多くの料理に寄り添える設計にしています。
Q. “甘さ控えめ”が重要な理由は?
播磨: 過度な甘みは料理の味わいをマスキングしてしまいます。ただ、甘みは料理との重なりのフックにもなる。
要素の一つとして甘さを適切に残し、他要素と結節させることで、料理を殺さずに「相性の良さ」をつくれるようにしています。
3. 味わいの印象、楽しみ方

Q. 初めて飲んだ人が感じる印象は?
塚越: 情報がない状態で飲むと「よくわからないけど、美味しい」という感想になると思います。
飲み進め、情報を入れていくほどさらなる良さが開いていく。味は全く異なりますが、そういう体験はワインに似ているかもしれません。不思議な飲み物です。
Q. 他飲料(ワイン・ジュース・お茶)との違いは?
塚越: 原料を幾層にも重ねたことで、味わいが多角的に変化します。ブドウのニュアンスに紅茶の香りが重なるなど、単一素材では生まれない段階的な味わい、心地よい違和感、複雑さ。
さらに、ひと口ごとの温度に応じて表情が変わり、合わせる料理によっても引き出されるフレーバーが大きく異なる。その移ろい、多面性をぜひ楽しんでください。
4. 「料理と並走」するペアリング哲学
Q. ペアリングで意識していることは?
塚越: 香りや味だけの“部分最適”にこだわらず、全体のバランスと調和。ボディとテクスチャーまで含めて、皿とグラスの関係性を設計します。
Q. 各DOUXLESSにおすすめの一皿は?(一例)
塚越:今回は、DOUXLESSのラインナップのなかでもとりわけ人気の二種に合わせて、二皿をご用意しました。
(塚越氏はソムリエとしての卓越した腕前にとどまらず、調理の技もプロフェッショナルの域。ソムリエと料理人、双方の知見こそが、唯一無二のドリンクを生み出す原動力となっている)

— ヒラメのマリネにハーブのジュレと玉ねぎのムース、プラムを合わせた前菜。エレガントアップルとのペアリング。ハーブのフレーバーが柚子系の要素と重なり、薬味のようなアクセントで全体が締まります。

— 鴨のロースト 赤ワインソース 焦がし万願寺。カオスグレープとのペアリング。鴨とベリーの相性に加え、ドリンクのスパイシーさがスパイスを含む赤ワインソースや、万願寺唐辛子の青いフレーバー(山椒に似たニュアンス)と重層的に絡む構成。上記2品は塚越がオーナーを務めるtanerで、実際に提供されている。
Q. ワインと比べて、どんな“体験の違い”を提供したい?
播磨: 違いを強調するのではなく、体験価値をワインに近づけることが重要だと考えています。
とりわけファインダイニングでの体験の幅広さはワインの強みです。その幅に非アルコールで追随し、新しい選択肢としてテーブル体験の価値を拡張したい。そしてこの価値をさらに磨き込むことで、ワインと“ジャンル”として並び立つ未来が必ず来ると確信しています。
5. 家庭での楽しみ方と今後

Q. 特別な日と日常の使い分けは?
播磨:クオリティは“ワインに遜色ない”レベルを目指しています。価格帯も“そこそこ良いワイン”の位置づけです。日常使いでも、ハレの日やちょっとした良い日でも、どちらでも問題ありません。
さらに、今年の販売開始を見据えて手に取りやすいカジュアルラインも用意しています。普段使いはそちら、ハレの日はDOUXLESS――という使い分けもおすすめです。
Q. 家庭で楽しむなら、どんな合わせ方が良い?
塚越: 日常の料理で大丈夫です。ただし提供の仕方で印象が変わるので、ワイングラスを使い、温度にも少し気を配ってください。
Q. 飲まない/飲めない人への新しい体験価値は?
塚越: ペアリングの楽しさそのものです。これまで触れづらかった文化にアクセスでき、食体験全体の“底上げ”につながるはずです。
終わりに
“Not juice, Not tea.”
既存カテゴリーの延長ではなく、料理と並走するための設計思想と手間を積み重ねて生まれたのがDOUXLESS。ワインと同じテーブルで、もう一つの正解を増やす——その挑戦が、外食でも家庭でも、食の景色を静かに塗り替えていきます。
塚越 慎之介プロフィール
taner オーナー兼ソムリエ
フランス パティスリーモネにて研修後 帰国、阿佐ヶ谷 "La maison courtine"、吉祥寺 "TEA MARKET Gclef、代々木上原 "sio" などでソムリエを経て現職。日本ソムリエ協会が発行するソムリエ資格だけではなく、日本ラム協会が発行するラムコンシェルジュ資格、日本スペシャルティコーヒー協会が発行するコーヒーマイスター資格、またコーヒーマスターズ 2016 全国 3位など、ワインに限らず液体全体への造詣が深い。2024年に落ち着いた空間でワインとフレンチを楽しめる「taner」を開業。
INFORMATION

〒165-0026
東京都中野区新井1-14-15